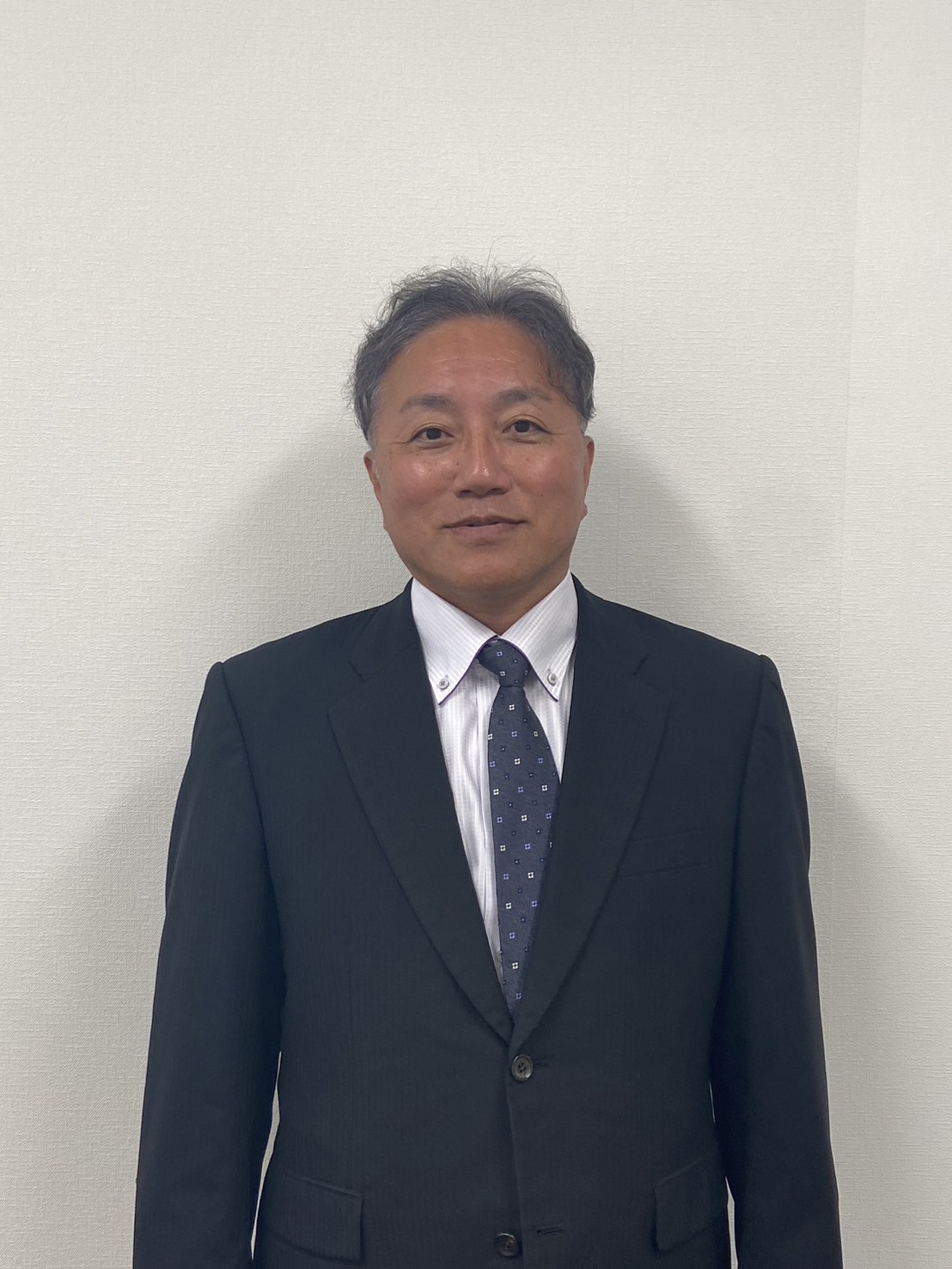
次世代をつくる
誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう支援ができるような社会をつくっていく。いわゆる医師の視点ではなく生活者の視点にたつ「地域包括ケア」の概念。
そして、日常的に頻度が高く、幅広い領域の疾病と傷害等について、適切な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供し、一方で「地域を診る医師」として、他の領域別専門医や他職種と連携して多様な医療サービスを包括的かつ柔軟に提供する「総合診療医」。
地域包括ケアの次の展開をリードしていく私たちのチャレンジを是非ごらんください。
特別教授:伊東 芳郎
総合診療医とは
主に地域を支える診療所や病院において、他の領域別専門医、一般の医師、歯科医師、医療や健康に関わるその他の職種などと連携し、地域の医療、介護、保健など様々な分野でリーダーシップを発揮しつつ、多様な医療サービスを包括的かつ柔軟に提供する医師を言います。
講座の目的
地域医療に関する教育研究を通じて、医学部生に地域医療への関心を喚起するとともに、地域医療に志を持つ医師のキャリアアップ等について支援することにより、へき地医療をはじめとする県内各地において地域医療を担う医師を養成・確保すること、専門性を兼ね備えた総合診療能力を有する医師の養成を目的としています。
我々の誓い
Our commitment
地域医療・総合診療領域における診療や教育、研究などの全ての領域において当講座は最善のものを提供できるように努力します。
我々のミッション
Our mission
地域医療・総合診療領域において最も質の高い診療・教育・研究およびリーダーシップをもって、私たちの患者さんや地域に貢献します。
我々のビジョン
Our vision
総合診療を様々な設定で、最善のものを提供することにより、次世代の医療人育成に貢献し、プライマリ・ケアがよりよいものになるように支援しながら成長する組織になります。

